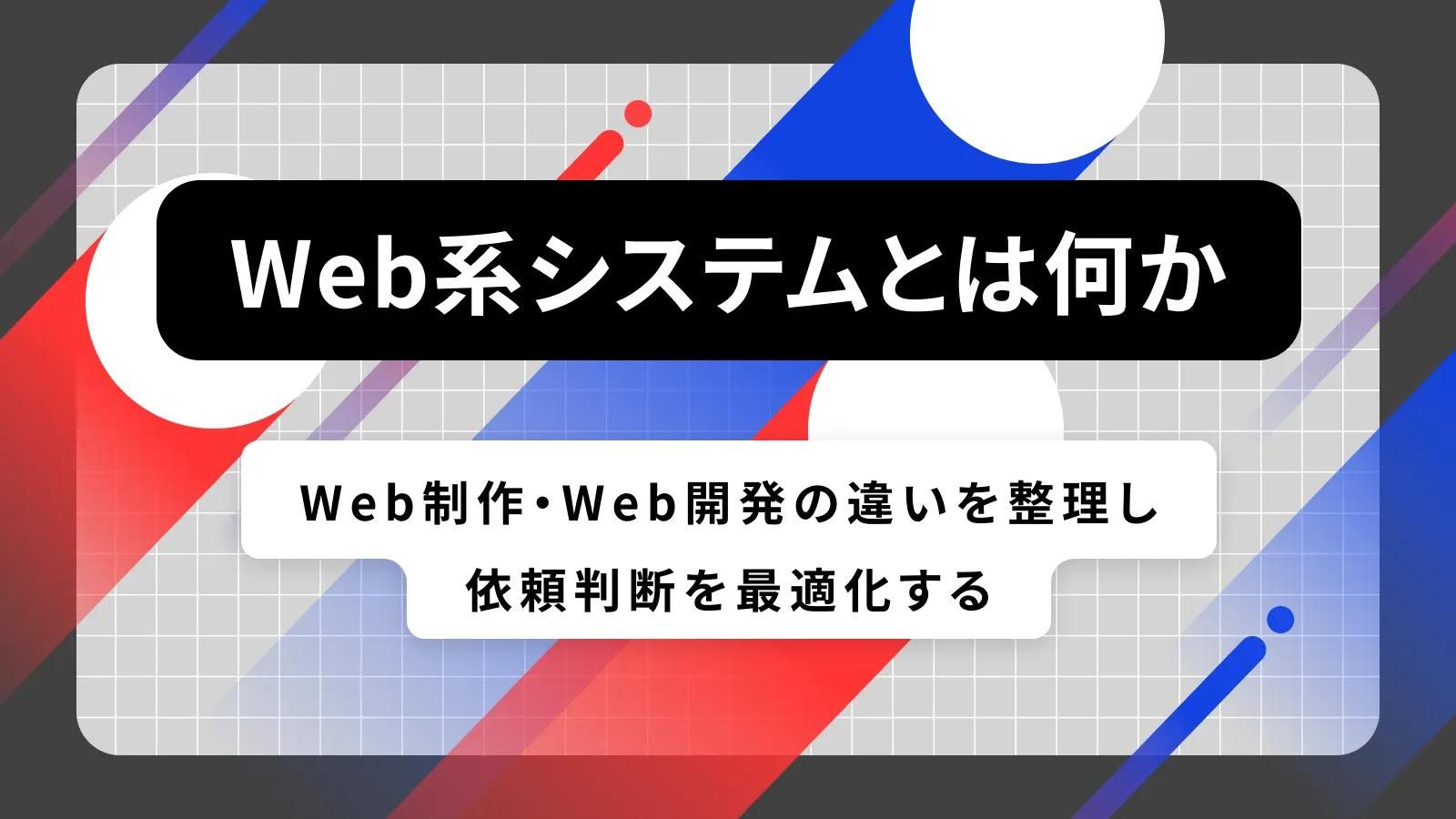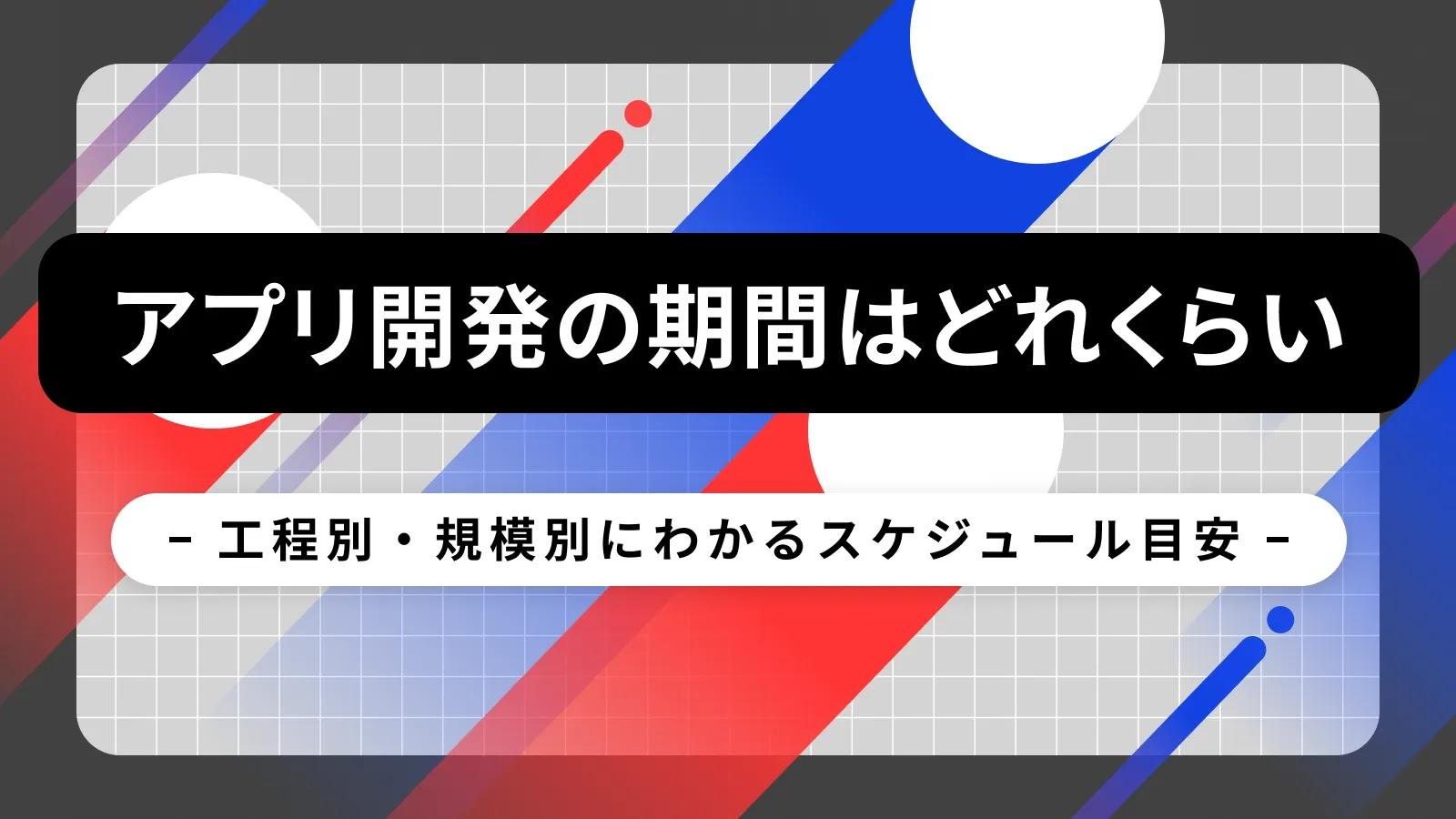アクセシビリティチェックの方法と義務化対策|色・構造・ツールで徹底解説
- Web制作

デジタルコンテンツやWebサイトの利用者が多様化する現代において、「アクセシビリティ対応」は企業や公共機関にとって避けて通れない重要課題です。特に日本でも法的義務化が進む中で、視覚・聴覚にハンディのあるユーザーを含め、誰もが公平にアクセスできるWeb設計が求められています。本記事では、「アクセシビリティチェック」の基本的な考え方から、具体的なチェック方法、色の見え方に配慮した設計、チェックツールの紹介まで、実務者がすぐに活用できるノウハウを徹底的に解説します。
アクセシビリティチェックとは何か?
アクセシビリティの定義と目的
アクセシビリティとは、インターネットやアプリケーションを含むすべての情報通信手段において、誰もが差別されることなく等しくアクセスできる状態を指します。これは障害の有無にかかわらず、全ての人々に公平な情報提供を行うための基礎的な考え方です。特にWebサイトでは、視覚・聴覚・身体的制限を持つユーザーにも配慮した設計が必要とされます。
Webアクセシビリティの目的は、単なる「デザインの見やすさ」ではなく、誰でも問題なく操作できる「利用しやすさ」の提供にあります。これはUX(ユーザーエクスペリエンス)の向上に直結し、ひいてはWebサイトの離脱率改善やCVR(コンバージョン率)の向上にも寄与します。
対象ユーザーと対応が必要な理由
アクセシビリティ対応が必要なユーザーは以下のように多岐にわたります。
- 色覚障害を持つユーザー:日本国内では男性の約5%、女性の約0.2%が色覚異常を持っているとされます。
- 高齢者:加齢によって視力・聴力・認知能力が低下し、一般的なUIでは操作が難しくなる場合があります。
- 視覚障害者:スクリーンリーダーを利用してWebコンテンツを音声で読み取るため、HTMLの構造的な正確性が求められます。
- 身体障害者:キーボード操作や視線・音声によるナビゲーションを補助機器で行うケースもあり、操作性の高い設計が必要です。
こうしたユーザーが不便を感じるサイトは、情報へのアクセスを拒むことになり、結果としてサービス機会の損失を招きます。企業や公共団体が積極的に対応することは、インクルーシブな社会形成の一助となります。
W3CやWCAGとの関連性
国際的にアクセシビリティ基準の中核を担うのが、WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)です。これはW3C(World Wide Web Consortium)によって策定されており、Webサイトにおけるアクセシビリティの技術要件が定義されています。
WCAGには「知覚可能」「操作可能」「理解可能」「堅牢性」の4つの原則があり、それぞれに対して達成基準が設けられています。日本国内においても、これに準拠した形でJIS X 8341-3:2016という規格が整備されており、公共団体や民間企業に対してその対応が推奨・義務化されています。
アクセシビリティ対応の義務化と背景
日本における法制度(障害者差別解消法など)
2016年に施行された「障害者差別解消法」は、障害のある人への不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を義務づけています。当初は国や地方自治体に限定されていましたが、2024年4月の法改正により、全ての民間事業者にも義務化されました。
この合理的配慮には、Webサイトやアプリなどのデジタルコンテンツも含まれ、アクセシビリティを担保した設計・開発が求められるようになっています。たとえば、「読み上げ対応のないPDFを送る」ことや、「音声案内がない動画を掲載する」ことなどは、障害者の情報取得機会を妨げる可能性があるため、配慮が必要です。
企業・自治体が求められる対応レベル
地方自治体や行政機関では、JIS X 8341-3の「達成等級AA」を満たすことが努力目標とされ、予算編成や調達要件にも影響を及ぼしています。また、教育機関や医療機関も同様の対応が求められており、Webアクセシビリティへの取り組みが遅れると、入札や契約における機会損失につながるリスクもあります。
一方、民間企業においても、近年はCSR(企業の社会的責任)やESG投資(環境・社会・ガバナンス)などの観点から、アクセシビリティ対応をブランド価値向上の一環として位置づける動きが進んでいます。
SDGsやDEIの観点からの重要性
「誰一人取り残さない(Leave No One Behind)」というSDGsの理念は、Webアクセシビリティの本質ともいえる目標です。また、DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)の考え方が広がる中で、障害を持つ方にも等しくサービスを提供できる体制づくりが、企業評価に直結するようになっています。
従業員や顧客の多様性を尊重する企業姿勢を、Web上の体験でも示すことが、次世代の企業ブランディングには欠かせません。
アクセシビリティチェックの基本ステップ
事前準備と対象範囲の明確化
チェック作業をスムーズに進めるには、初期段階での準備が重要です。
- 対象ページの洗い出し:全体のURLリストを作成し、優先度の高いページ(トップページ、採用、商品ページなど)から順に実施。
- チェック基準の明確化:WCAG 2.1の等級AAをベースに、独自の基準を追加するケースもあります。
- ツールや検証環境の整備:Chrome拡張機能やスクリーンリーダー(NVDA、VoiceOver等)の用意も必要です。
これらを明確にしておくことで、属人化やチェック漏れを防ぐことができます。
特定の担当者に依存しない仕組みができれば、メンバー交代時にも対応がスムーズです。
また、対象範囲が曖昧だとチェックが重複したり漏れたりする原因にもなります。
準備フェーズを丁寧に設計することが、全体の作業効率や品質を大きく左右します。
チェックリストに基づく評価方法
評価の際には、下記のような項目が含まれるチェックリストを使用します。
- 画像に適切なalt属性が設定されているか
- 見出し構造が論理的に整っているか(H1→H2→H3の順序)
- キーボードだけで全ての操作が可能か
- 文字と背景のコントラスト比が基準以上か(4.5:1以上)
- リンクテキストが文脈で意味を成しているか
すべての項目を確認し、未達成箇所を明示することで、改善作業の優先順位付けが容易になります。
単に達成・未達の二択ではなく、改善インパクトやユーザーへの影響度も加味すると効果的です。
評価に基づいてリスクの高い箇所から順に対応すれば、全体のアクセシビリティレベルが向上します。
また、チェックリストは社内で標準化し、運用ルールとして定着させることが理想です。
レポート作成と改善サイクル
評価結果はレポートとして文書化し、以下のような項目を記載します。
- 対応状況(達成/未達)
- 改善が必要な箇所と理由
- 改善策と担当者のアサイン
これにより、プロジェクトメンバー全体の認識統一が図れ、次回以降の検証プロセスにも活用できます。
関係者が同じ課題意識とゴールを共有することで、改善のスピードと精度が向上します。
レポートは単なる記録ではなく、チーム全体でPDCAサイクルを回す起点として機能します。
月次レビューや公開前レビューのサイクルを定着させることで、継続的な品質担保が可能です。
色のアクセシビリティチェックと配慮方法
色覚特性と見え方の違い
色覚にはさまざまなタイプがあり、多くの人にとって当たり前の色の見え方が、色覚異常のある方には大きく異なって映ります。特に「赤と緑」、「青と紫」、「オレンジと黄緑」などの組み合わせは、識別が困難です。
このため、色の違いだけで情報を伝えないことが重要です。
たとえば「赤文字で注意喚起」など、色に依存した伝達方法は誤解や見落としを生む恐れがあります。
色覚多様性に配慮することで、より多くのユーザーに正確な情報を届けることができます。
情報は「形・テキスト・アイコン」など複数の手段で補完するのが理想的です。
配色設計における注意点と改善例
アクセシビリティ配慮の基本は「コントラスト」と「情報の冗長性」です。改善例を以下に示します。
NG例:赤文字で「エラー」と表示するのみ
改善例:黒文字+赤アイコン+「×エラー」の表記+灰色背景で強調
また、グラフでは色分けだけでなく、パターンや凡例も併用することが推奨されます。
色だけに頼らず、誰にとっても理解できるように視覚情報を重層的に設計することで、誤読や操作ミスを減らすことができます。
特に業務系や医療系の画面では、視認性の確保がユーザー体験の安全性にも直結します。
色のコントラスト比チェックツール紹介
視認性を確認するツールの一例として、以下のようなものがあります。
WebAIM Color Contrast Checker:2色のRGBコードを入力することで、WCAG基準を満たしているかをチェック可能。
Color Oracle:実際の画面を色覚異常のパターンでシミュレーションし、見え方を確認。
axe DevTools(Chrome拡張):UI全体の自動チェック機能を備え、コントラストの警告も表示。
これらを活用して、より実環境に近いチェックを行いましょう。
手動では気づきにくい微妙なコントラスト差や、ユーザータイプごとの見え方の違いを視覚的に把握できるため、客観的な改善判断にもつながります。
アクセシビリティチェックツールの紹介
無料・有料ツールの特徴比較
| ツール名 | 無料/有料 | 特徴 |
|---|---|---|
| axe DevTools | 無料+有料 | 自動診断+ブラウザ連携が便利 |
| WAVE | 無料 | 見た目で問題箇所が分かりやすい |
| Siteimprove | 有料 | 多言語サイト対応・大規模案件向け |
主要なチェックツール(axe、WAVE、Color Oracleなど)
- axe DevTools:HTML構造、ARIA属性、コントラストまで幅広く自動チェック。
- WAVE:視覚的な指摘が分かりやすく、開発者だけでなくマーケティング担当者にも向いています。
- Color Oracle:3つの主要な色覚異常(P型・D型・T型)に対応。Windows/Mac両方で使用可能。
ツールは単独で完璧な診断ができるわけではないため、複数の併用が望まれます。
導入・運用時の注意点と実践方法
自動チェックだけで完結させず、人の目による最終確認が必須
アクセシビリティ検証では、axeなどの自動ツールが便利ですが、完全ではありません。
文脈に応じたaltテキストの妥当性や、視線の流れに対する違和感などは、ツールだけでは判断できません。
そのため、最終的には実際のユーザー視点での確認が不可欠です。
スクリーンリーダーの読み上げ結果や、キーボード操作の感触なども人が操作してこそ見える課題があります。
継続的なチェック体制を構築(公開前・定期レビューなど)
一度チェックして終わりではなく、コンテンツの追加や更新ごとに再確認する体制が重要です。
公開前レビューに加え、月次・四半期など定期的な再チェックのルールを設けましょう。
CMSのテンプレート更新やデザイン改修時にも、アクセシビリティ要件が崩れていないかを確認する必要があります。
継続的な運用が、品質の維持と改善サイクルの確立につながります。
担当者の教育・理解促進もあわせて行うと効果的
担当者がアクセシビリティの基本を理解していないと、形だけの対応で終わってしまう恐れがあります。
WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)の考え方やツールの使い方、ユーザー視点でのチェック方法などを定期的に学べる仕組みを用意しましょう。
チーム内で知識を共有することで、属人化を防ぎ、チェック精度を安定させることができます。
社内研修やeラーニング、外部セミナーの活用も有効です。
まとめ
アクセシビリティチェックは、単なる法令対応やCSR活動ではなく、「誰もが使えるデジタルサービス」を提供するための土台です。企業や自治体が率先して取り組むことで、ユーザーからの信頼獲得、ブランドイメージの向上、さらにはWebサイトの成果最大化にもつながります。
アクセシビリティ対応に課題を感じている企業様へ
当社では、現状分析から具体的な改善提案まで一貫したサポートをご提供しています。まずはお気軽にお問い合わせください。経験豊富な専門スタッフが、貴社のWebアクセシビリティレベル向上をお手伝いします。
「アクセシビリティチェックの方法と義務化対策|色・構造・ツールで徹底解説」
の詳細が気になる方は、
お気軽にお問い合わせください

Y's Blog 編集部