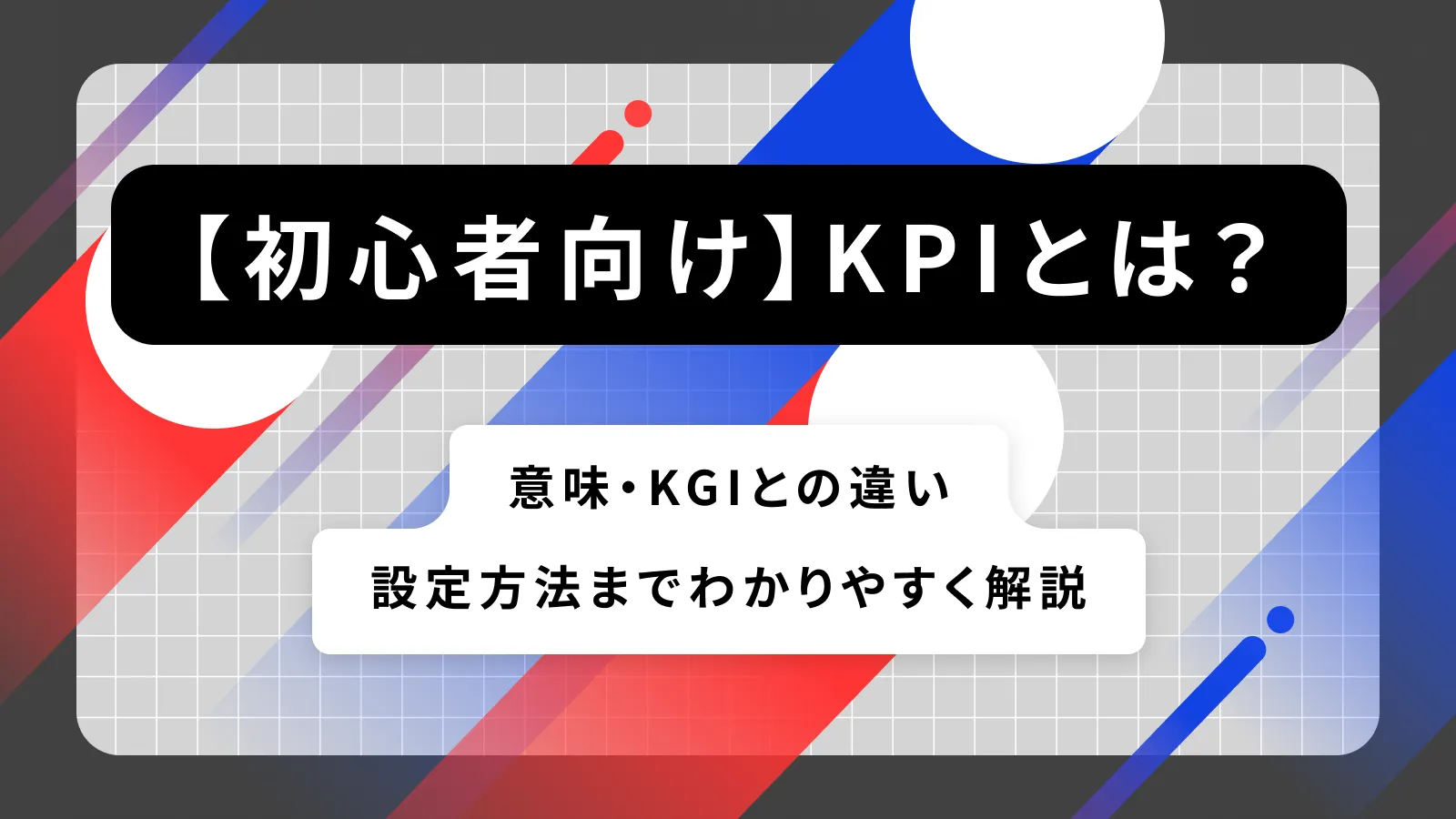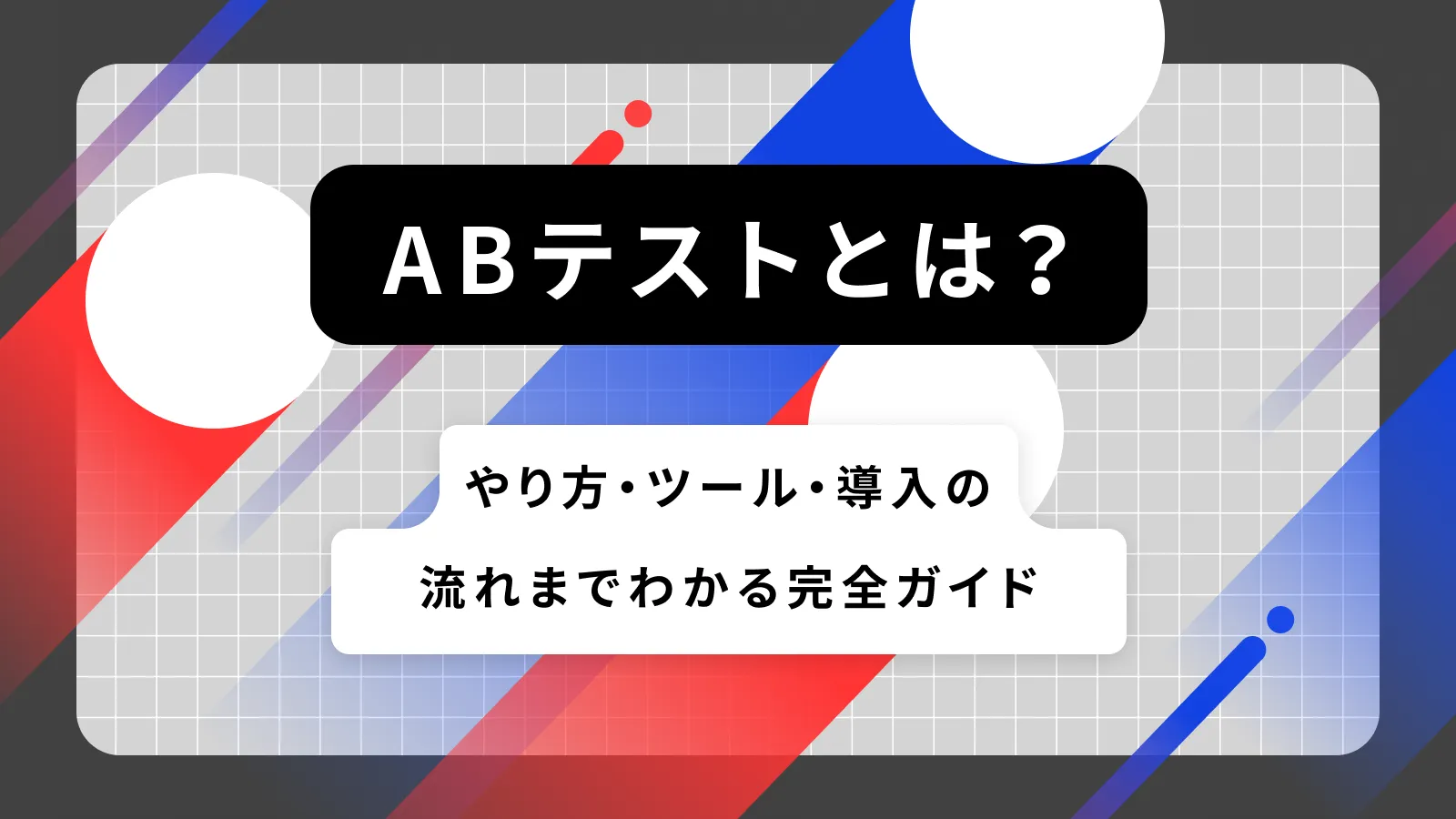ランディングページ改善の極意|成果につながるLPO施策と成功事例を解説
- Web制作
- Webマーケティング

目次
ランディングページ改善の基本とは?
LPO(ランディングページ最適化)とは何か
LPO(Landing Page Optimization)とは、訪問者がランディングページに到達した際の行動を最適化し、最終的にコンバージョン率(CVR)を向上させるための施策全般を指します。具体的には、訪問者が求めている情報にスムーズにアクセスできるようにランディングページの導線を整えることです。これにより、直帰を防ぎ、CV(コンバージョン)への導線を強化します。
成功するLPOは、単にビジュアルやコンテンツを整えることにとどまらず、UI(ユーザーインターフェース)の改善を通じて、ユーザーの行動を促進します。つまり、LPOの最終目的は、ページを訪問したユーザーに対して「欲しい情報」を直感的に伝え、アクションを促すことです。この過程を最適化することで、コンバージョン率が大きく向上し、広告費用対効果(ROAS)が改善されます。
ユーザー視点とマーケティング視点の両方を兼ね備えるLPOは、顧客のニーズに即した改善策を講じるため、ビジュアルデザイン、情報設計、そしてユーザーインターフェースを総合的に見直す必要があります。これにより、LP全体の効果を最大化し、ユーザー体験(UX)を向上させることが可能になります。

改善が必要なサインと指標
ランディングページ(LP)のパフォーマンスが思わしくない場合、特定の数値指標が改善のサインとなります。これらの指標は、改善施策を実施する前に明確に確認し、問題の早期発見に役立てるべきです。以下は、一般的にLPのパフォーマンスが低迷しているサインとなる指標です。
- 直帰率が高い(80%以上)
直帰率が高い場合、LP自体に魅力がないか、訪問者が求めている情報が即座に見つからないことを示唆しています。直帰率が80%以上の場合は、特に改善が急務です。
- 滞在時間が極端に短い(平均30秒未満)
訪問者がサイトに滞在している時間が非常に短い場合、コンテンツが魅力的でないか、またはユーザーの求める情報がすぐに得られない可能性があります。滞在時間が短いと、エンゲージメントも低くなり、CVへの道筋が閉ざされてしまいます。
- スクロール率が低い(ファーストビューからの離脱)
LPに訪問してもファーストビューから先に進まずに離脱してしまう場合、デザインや情報の配置に問題があることが考えられます。ファーストビューがユーザーに与える第一印象は非常に重要であり、ここで惹きつけられなければその後の行動を促すのは難しいです。
- コンバージョン率が低迷している(CVRが1%未満)
コンバージョン率(CVR)が1%未満の場合、LP全体の最適化が必要です。目標とするコンバージョンに繋がっていない可能性が高く、フォームやCTAの改善が重要です。
これらの指標は、LP改善のタイミングを見極めるための目安として活用できます。Googleアナリティクスやヒートマップツールを使用し、これらのデータを分析することで、どの部分に問題があるのかを可視化しやすくなります。定期的に指標を確認し、早期に問題を特定して改善策を講じることがLPOの成功に繋がります。
ランディングページ改善を行う際の全体の流れ
課題の洗い出しとKPI設定
最初に行うべきは、現状のLPが抱える問題を明確にすることです。
「直帰率が高い」「CVRが低い」「滞在時間が短い」など、数値的な問題点を整理しましょう。
そのうえで、改善のゴールとなるKPI(例:CVR3%以上、直帰率60%以下など)を設定します。明確な指標を持つことで、施策の成否を判断しやすくなります。
LPに来訪しているユーザーのアクセス分析
ユーザーがページ内でどのように行動しているかを把握するには、ヒートマップやアクセス解析ツールが有効です。これらを活用することで、クリックされた場所、スクロールの到達率、離脱したタイミングなどが視覚的にわかり、ユーザーの動線を具体的に捉えることができます。
たとえば、CTAボタンが他の要素に埋もれて目立たずクリックされていない、ファーストビューの時点で多くのユーザーが離脱してしまっている、あるいはフォームまで到達するユーザーが極端に少ない、といった問題点が浮き彫りになります。
こうしたデータに基づいた可視化は、改善の優先順位を明確にし、的確な施策へとつなげるための出発点となります。
問題点を洗い出す
ユーザー行動のデータをもとに、コンテンツ構成やデザイン、導線にどんな課題があるのかを深掘りします。
たとえば、キャッチコピーの弱さや、訴求内容と画像の不一致、情報の順序が分かりづらい構成、フォーム項目が多すぎて離脱を招いているケースなどが典型です。
こうした構造的な問題を見つけることが、効果的な改善への第一歩になります。
仮説を立て、対策を決める
課題を洗い出したあとは、「なぜその問題が起きているのか?」という仮説を立てて原因を探ります。
たとえば、「キャッチコピーが具体性に欠け、ユーザーの関心を引けていないのでは?」
あるいは、「CTAが画面下にしかなく、見逃されているのでは?」 といった形です。
この仮説をもとに改善施策を立てていきます。仮説と施策がしっかり結びついているかどうかが、LPOの成果を大きく左右します。
施策実行と検証
仮説に基づいた改善施策をLPに反映させた後は、ABテストや多変量テストなどで効果を検証します。
ここで重要なのは、一度に複数箇所を変更しすぎないこと。テストは「1回につき1つの要素」に絞ることで、何が効果をもたらしたのかを明確にできます。
改善サイクルの定着方法
LP改善は一度きりではなく、検証結果から新たな仮説を立て、施策を繰り返すPDCAサイクルが不可欠です。
これを組織に定着させるには、以下のような体制づくりが重要になります。
- 定期的にレビューを行う場を設ける
- KPIのモニタリングを自動化する
- ツールやデータ活用のルールを標準化する
こうした仕組みを並行して整えることで、継続的な改善がスムーズに進みます。
ランディングページ改善方法チェックリスト
ファーストビューは最適化されているか?
訪問者が最初に目にする「ファーストビュー」は、LP全体の成果を左右する最重要エリアです。
ユーザーは数秒で「自分に関係があるかどうか」を判断するため、この部分で「何を」「誰に」「どう伝えるか」を明確に整理することが不可欠です。
①キャッチコピーを改善する
ファーストビューの中心となるキャッチコピーは、以下のポイントを意識して改善しましょう。
| 改善ポイント | 内容の説明 | 具体例 |
| ベネフィットが具体的か | 明確な効果を示してユーザーの関心を引く | 「導入で工数70%削減」 |
| ターゲットを絞ったメッセージか | 対象ユーザーをはっきりさせる | 「人事担当者のための…」 |
| 一目で理解できるか | 長すぎず抽象的な表現は避け、シンプルに | シンプルで直感的に伝わる文言 |
【改善例】
「Web接客で売上UP」→「月商1.5倍!ECサイト向けWeb接客ツール」
数字を使って説得力を高めると効果的です。
②ファーストビューの画像を改善する
第一印象を左右する画像は、キャッチコピーと同じくらい重要です。以下のポイントを押さえましょう。
- 訴求メッセージと画像が連動しているか
- ターゲットの共感を得られるビジュアルか
- 画質やトリミング、余白に配慮されているか
- 動画やアニメーションで視覚的インパクトを強めるのも効果的
例として、SaaSなら「使いやすそうな管理画面のスクリーンショット」、美容系LPなら「Before→Afterの比較画像」など、ユーザーがサービス利用や効果をイメージしやすい画像が効果的です。
③トップ以外の画像では「キャプション」をつけると効果的なこともある
画像だけでは伝わりにくい場合が多いため、特にスクロール後の画像には短い説明文(キャプション)をつけると理解度が高まります。
キャプションのポイント
- 数字や実績を盛り込む(例:「累計10,000社が導入」)
- 権威性を示す(例:「経済産業省採用の実績あり」)
- 画像と合わせてストーリーを伝える(例:「導入前の状態はこちら」)
画像は単なる飾りではなく、情報を伝える重要な要素として活用しましょう。
CTAは魅力的か?
ランディングページの最終的なゴールを達成するために欠かせないのが、CTA(Call To Action=行動喚起)です。
「申し込み」「資料請求」「問い合わせ」など、ユーザーに行動を促す要素が明確かつ魅力的でなければ、どれだけ内容が良くてもコンバージョンにはつながりません。
以下の3点を軸に、CTAを見直してみましょう。
①申し込みボタンの文言を変える

ボタンのテキストは、ただ「申し込む」「送信する」ではなく、ユーザーの心理に寄り添った表現が効果的です。
改善のコツとして、
- 行動の目的を具体化する
- ×「送信」 → ○「無料で資料を受け取る」
- 不安を取り除く表現にする
- ×「今すぐ申し込む」 → ○「まずは無料で試してみる」
- 得られる価値を伝える
- ×「登録」 → ○「〇〇の始め方を受け取る」
ベネフィットを想像できる言葉を使うことで、クリック率が大きくアップします。
②ボタンのデザインを改善する

見た目はユーザーの目を引くために非常に重要です。目立たなければ、クリックされることはありません。
改善のチェックポイント
- 色
周囲としっかりコントラストがついているか?
例:背景が白なら、赤やオレンジなど暖色系が効果的。 - サイズ
スマホでも押しやすい大きさかどうか。 - 形状
角を丸くすると柔らかい印象に。 - 動き
ホバーやクリック時のアニメーションで反応を促す。
視認性と操作性を高めることが、コンバージョン率向上につながります。
③ボタンの数や位置を改善する

ボタンが1つしかない、あるいは多すぎる場合、ユーザーは行動を起こしづらくなります。
【改善のポイント】
- 複数配置が基本
→スクロールが必要なLPなら、ファーストビュー、中間、下部などにバランスよく設置しましょう。 - 文言やリンク先を目的別に使い分け、適切なものにする
- ユーザー心理に合わせて配置する
→説明を読んだ後にボタンがあると、CV率が高くなることがあります。
行動を誘導するという視点で、ボタンの「場所」も設計しましょう。
CTAの改善は、LPOの中でも成果に直結しやすい領域です。
「言葉・見た目・配置」の3つを意識して、テストと改善を繰り返すことで大きな成果が期待できます。
フォームで離脱を防げているか?
ランディングページで最も多くの離脱が発生するのがフォーム入力のタイミングです。
「もう少しでコンバージョン」という段階での離脱を防ぐためには、ユーザーがストレスなく入力できる設計が欠かせません。
以下の4つの観点から、フォームの最適化を進めましょう。
①入力の手間を少なくする
フォームの入力項目が多すぎると、ユーザーは「面倒」と感じて離脱してしまいます。完了率を高めるには、入力の負担をできるだけ減らすことが重要です。
【今すぐ試せる改善案】
- 本当に必要な項目だけに絞る(理想は3~5項目)
- 住所・会社名・部署名などは後回しでもOK
- 選択肢(プルダウン・チェックボックス)を活用して入力を簡略化
- GoogleやSNSアカウント連携での自動入力も検討
フォーム完了までのストレスが軽減され、コンバージョン率の向上が期待できます。
②エラーの箇所をわかりやすくする

ユーザーがフォーム入力中にエラーに遭遇した際、「どこが間違っているのか分からない」「どう直せばいいのか不明」といった状況になると、ストレスを感じて離脱につながります。
そのため、エラーの箇所を色やアイコン、補足メッセージで明確に示す設計が必要です。たとえば「エラーがあります」ではなく、「メールアドレスの形式が正しくありません」といったように、できるだけ具体的に伝えることでユーザーの混乱を防げます。
さらに、入力中にリアルタイムでエラーを通知する「即時バリデーション」も有効です。入力ミスがあってもすぐに気づき、スムーズに修正できるため、安心感を与えるとともに完了率の向上にもつながります。
③画面を見やすく、操作しやすくする
フォームの見た目や操作性も、ユーザーの入力体験に大きく影響します。デザインがごちゃついていたり、スマホで使いにくかったりすると、それだけで離脱の原因になってしまいます。
【具体的な改善例】
- 余白をしっかりとり、詰め込みすぎない
- PC・スマホ両方で使いやすいレイアウトに対応(レスポンシブ対応)
- スマホでは「入力項目に応じたキーボード(数字・メールなど)」が自動で出るようにする
- 送信ボタンが押しやすい位置にあるか確認
視認性や操作性に配慮することで、フォーム完了率が改善されます。
下記は郵便番号の入力の改善案

④LPとフォームを一体化する

LPを読んでから別ページに遷移して入力」という流れは、ユーザーの集中を途切れさせ、離脱のリスクを高めてしまいます。そのため、フォームはできるだけLP内に組み込むのが理想的です。
たとえば、ページ下部にそのまま入力できる埋め込み型のフォームを設置すれば、スムーズにコンバージョンへとつなげられます。また、CTAをクリックした際にポップアップでフォームを表示したり、2〜3ステップで少しずつ質問を進める「ステップフォーム」を使うことで、心理的なハードルを下げることも可能です。
大切なのは、ユーザーの導線を途切れさせず、「流れるように入力・送信」できる体験を提供すること。フォーム改善は、見た目以上にCVRに直結する重要な要素です。
迷わせず・手間を感じさせず・不安にさせない。この3つを軸に、一貫性のある構成を目指しましょう。
訴求内容と導線は整理されているか?
LP内で「何を伝えたいのか」がぼやけていると、ユーザーは途中で迷い、離脱やCV率低下の原因になります。訴求軸と情報の流れがブレていないか、以下のポイントで確認しましょう。
| チェックポイント | ポイント・補足例 |
| 訴求は“1ページ1メッセージ”が基本 | 多くの情報を詰め込みすぎると焦点がぼやける |
| 冒頭で「メリット・問題解決・対象ユーザー」を明示 | 「これは自分に関係がある」と思わせる導入が重要 |
| 情報の流れは設計通りか? | 「課題提示 → 解決策 → 実績・信頼性 → CTA」の順が効果的 |
| クリックやスクロールの導線にムダがないか? | ユーザーが迷わずCTAまでたどり着けるかをチェック |
LP全体を通じて、「誰に」「何を伝え」「どう行動してほしいのか」がクリアになっている状態が理想です。
構成に迷ったら、一度ワイヤーフレームに落とし込んで全体の流れを俯瞰するのも効果的です。
LP構成はユーザーにとって読みやすいか?
どれだけ内容が良くても、構成や見た目が読みづらければ、情報は届きません。
LPの読みやすさを高めるには、「視線の流れ」「情報の整理」「スマホ対応」といった基本が非常に重要です。
特にチェックしたいポイントは以下の4つです。
- 1セクションごとに情報を区切り、見出しで構造化する
→まとまりのあるレイアウトは、読み進めやすさを生みます。 - 箇条書きやアイコンを使い、視線が流れやすくなる工夫を
→文章だけで構成されたページは、ユーザーの集中力が続きません。 - 重要な箇所には装飾(強調色、太字など)を使う
→情報の優先順位を視覚的に伝えましょう。 - スマホでも読みやすいサイズか確認
→文字が小さすぎたり、要素が詰まりすぎていないかを必ずチェック。
ユーザーにストレスを与えず、自然に読み進められる構成こそが、LP成果の土台になります。画像や図を活用して視覚的に補助するのも効果的です。

LPの表示速度はユーザーにとってストレスがないか?
LPの表示速度が遅いと、多くのユーザーがすぐ離脱してしまいます。
特にスマホでは速度がCVRに直結するため、画像の軽量化や不要なスクリプトの削減、サーバーやCDNの最適化が重要です。Google PageSpeed InsightsやLighthouseで定期的にチェックし、見た目のリッチさと表示速度のバランスを保ちましょう。

アンケートの埋め込みなど、+α工夫ができているか?

LP内にユーザーと軽く接点を持てる+αの要素を設けることで、離脱率の改善やコンバージョン以外の接点獲得が期待できます。例えば、
- 「今どんなことで悩んでいますか?」といった簡単なアンケート、
- チャットボットや1問診断ツールの活用、
- 「おすすめプランを診断する」などの選択式コンテンツ
といった方法です。単に情報を見せるだけでなく、ユーザーが参加できる仕組みを作ることで、関心を引きつける効果的な導線になります。
流入経路に合わせて最適なLPの出し分けができているか?
同じ内容のLPを、すべてのユーザーに見せていては成果を最大化できません。
流入経路(広告/自然検索/SNSなど)やターゲット属性に応じて、出し分ける設計が必要です。
【出し分けの例】
- リスティング広告→検索キーワードに応じたLPへ
- SNS→共感系ストーリーを強めたLPへ
- リターゲティング→導入実績や信頼性重視のLPへ
配信元の「期待」とLPの「情報」が一致することで、コンバージョン率が高まります。
web接客の導入はできているか?
離脱寸前のユーザーに対して、Web接客(ポップアップやチャットボット)は非常に効果的です。例えば、スクロールはしているがコンバージョンに至らないユーザーに限定オファーを表示したり、滞在時間が長い訪問者にチャットで案内を提案したり、離脱しそうな動きを察知して出口ポップアップで再度アプローチしたりできます。
【活用シーンの例】
- スクロール率は高いがCVしないユーザーに限定オファーを表示
- 滞在時間が長い訪問者にチャットで案内を提案
- 離脱が予測されるユーザーに出口ポップアップを表示
代表的なツールにはKARTE、Zendesk、Chatbaseなどがあり、タイミングやターゲティングを工夫することで、自然で効果的な誘導が可能です。
こうした細かな施策の積み重ねがLP全体の成果を大きく向上させ、「全体設計」と「パーツ最適化」を両立することがLPO成功の鍵となります。
ユーザー視点に立った改善アプローチ
ペルソナ設計と訴求の一貫性
効果的なLPOを実現するためには、ターゲットユーザー像(ペルソナ)の設計が非常に重要です。ペルソナを明確にすることで、LP全体の訴求軸を統一でき、ユーザーにとって有益で魅力的な情報を提供することが可能になります。ペルソナ設計においては、以下の要素を意識して考えることが大切です。
年齢・職種・悩み・利用シーンなどの細かい属性設定
ペルソナを設計する際には、ターゲットとなるユーザーの年齢や職種、日常的な悩みや利用シーンを明確にしましょう。例えば、企業経営者向けのサービスであれば、定量的な成果や信頼感を強調した内容を提示することが効果的です。このように、ターゲットが直面している課題や求める解決策に焦点を当て、訴求内容を統一することで、ユーザーにとって一貫したメッセージを提供することができます。
訴求内容がずれると、ユーザーは違和感を覚え、離脱に繋がる
ペルソナ設計をしっかり行わずに訴求がずれてしまうと、ユーザーは内容に違和感を覚え、最終的には離脱してしまう可能性が高くなります。適切なペルソナ設定を行うことで、訪問者が自分に必要な情報を得ていると感じやすくなり、コンバージョン率(CVR)の向上につながります。
ヒートマップやABテストの活用
LPの改善において、定量的・定性的なデータを活用することは非常に重要です。これにより、訪問者の行動パターンを明確にし、どの要素が効果的であるか、または改善が必要かを判断することができます。代表的な分析ツールとしては、以下のものがあります。
ヒートマップ:どこでスクロールが止まっているか、どこがクリックされているかを可視化
ヒートマップツールを活用することで、ユーザーがページ上でどの部分に注目しているか、どこでスクロールを止めるのか、どこをクリックしているのかを視覚的に把握できます。これにより、重要な情報が埋もれてしまっている箇所や、逆にユーザーが無駄に集中している部分を特定し、改善を加えることができます。
ABテスト:異なるコピーやCTAを試し、成果が高い方を採用
ABテストは、異なるバージョンのLPを用意して、どちらがより多くのコンバージョンを生み出すかを検証する手法です。例えば、異なるキャッチコピーやCTA(Call to Action)の文言、デザインの変更を試して、成果が高い方を採用することで、効果的なランディングページを作り上げることができます。ABテストの結果をもとに、ユーザーの反応に最も効果的な要素を見つけ出しましょう。
ツール例:Mouseflow、Hotjar、Google Optimize など
これらのツールは、ユーザーの行動データを収集し、分析するために非常に役立ちます。例えば、MouseflowやHotjarでは、ヒートマップを使用してユーザーのマウスの動きやクリックの履歴を確認できますし、Google Optimizeでは、ABテストの実施と成果分析を簡単に行うことができます。これらのツールを駆使して、LPOの精度を高めることができます。
モバイル最適化の重要性
現在、Webサイトへのアクセスの過半数以上がスマートフォン経由であることから、モバイル最適化は必須の施策となっています。モバイル対応が不十分だと、ユーザー体験が悪化し、最終的にはコンバージョンが減少してしまいます。モバイル最適化を意識した設計は、成果に大きな影響を与えます。以下のポイントを押さえて、モバイル最適化を進めましょう。
レスポンシブ対応
レスポンシブデザインを採用することで、ユーザーがどのデバイスからでも最適な表示でコンテンツを閲覧できるようになります。スマートフォンでも見やすいレイアウトを実現し、ユーザーがストレスなくページを操作できるようにすることが重要です。これにより、スマホからのアクセスにも効果的に対応できます。
タップしやすいボタン配置
モバイル端末で操作する際、タッチ操作のしやすさは非常に重要です。ボタンのサイズや配置を適切に調整し、指でタップしやすくすることで、ユーザーが迷うことなくアクションを起こすことができます。ボタン間のスペースも十分に確保し、誤タップを防ぐように設計しましょう。
読み込み速度の高速化
モバイルユーザーにとって、ページの読み込み速度は非常に重要な要素です。特にスマートフォンでのインターネット環境は、Wi-Fiと比べて通信速度が遅い場合もあるため、ページの読み込みが遅いとユーザーが離脱する原因となります。画像の圧縮やJavaScriptの最適化を行い、ページの読み込み速度を高速化することで、より多くの訪問者を維持できます。
モバイルで見やすく・使いやすいことが、CV向上に直結
モバイルでの視認性と操作性の向上は、直帰率を低減し、コンバージョン率を向上させるために非常に効果的です。レスポンシブデザインやボタン配置の最適化、速度改善などの施策を通じて、モバイルユーザーにとって快適な環境を提供することが、最終的な成果に直結します。
ランディングページ改善の注意点
1回のテストで変える箇所は1つだけにする
ABテストを行う際、「複数の要素を同時に変更」してしまうと、何が効果につながったのか特定できなくなります。
改善点が曖昧なままでは、再現性のある成果につながりません。
理想は“1回1変更”。
まずはキャッチコピー → 次にCTAボタン → その後に構成…のように、要素ごとに分けて検証しましょう。
改善案の優先順位を決めて取り組む
改善すべき点が複数ある場合、どこから手をつけるかで成果の出やすさが大きく変わります。
優先順位を決める際の基準
- 数字への影響が大きいか(CVR直結の要素)
- ユーザー行動でボトルネックになっている箇所か(ファーストビュー/フォームなど)
- 改善コストが小さいか(短期間・少人数で対応できる)
「やりやすいところ」ではなく、「効果が高い×実行可能」な部分から着手しましょう。
問い合わせ数が増えたから成功ではない
LP改善で問い合わせ数が増えたからといって、それだけで成功とは言えません。問い合わせの質が伴わなければ、営業工数だけが増えてしまうリスクがあります。評価すべきポイントは次の通りです。
- 商談化率や受注率に変化はあるか
- 問い合わせの属性がターゲット層に合っているか
- LPの訴求内容にズレがないか(例:無料トライアル目的のユーザーが多いなど)
「数」だけでなく、「質」も必ず評価軸に入れることが重要です。
流入元・LP・フォームが一貫しているか
広告の訴求内容とLPやフォームのメッセージにズレがあると、ユーザーは混乱し離脱しやすくなります。
| 例示内容 | 問題点・ズレの内容 |
| 広告で無料トライアルを謳っているのに、LPでは有料プランしか掲載していない | ユーザーの期待と実際の内容にギャップが生まれ、離脱リスクが増す |
| 初心者向けを強調する広告に対し、LPが専門用語ばかり使っている | ターゲットユーザーが理解しづらく、混乱を招く |
| 導入の簡単さをアピールしているのに、フォームの入力項目が多すぎる | ユーザーの負担が増え、フォーム離脱の原因になる |
こうしたズレがあると、ユーザーは「期待と違う」と感じてしまいます。
そのため、流入元からLP、フォームまで訴求の一貫性をしっかり保つことが非常に重要です。
リンクを増やしすぎていないか?
リンクを増やしすぎるとユーザーの注意が分散し、本来の目的であるCTAへの導線が弱くなります。そのため、メニューや外部リンクはできるだけ減らし、詳細な説明はモーダルやFAQなどで補完することが大切です。また、CTA以外のクリックポイントを減らし、ユーザーの集中を促すことが効果的です。特にシングルページのLPでは、ユーザーを迷わせないシンプルな設計が基本となります。
信憑性のない口コミを多用していないか
「お客様の声」やレビューはCV率を高める重要な要素ですが、信憑性の低い口コミの多用は逆効果になることがあります。以下の点に注意しましょう。
- 顔写真・実名・肩書きなど具体性があるか
- 内容が抽象的すぎず、テンプレ化していないか
- サクラ的な演出になっていないか
できれば、動画の声やSNSの実名投稿などリアルな証言を引用し、信頼感を高めることが理想的です。
そもそもLPに大きな課題がないのにLP改善に取り組もうとしていないか
CVRが1.5%程度ある場合、無理にLP改善に注力する前に、他の要因を優先的に見直しましょう。具体的には、
- 流入元の質(広告のターゲティングやキーワード設定)
- 商品やサービス自体の競争力や価格設定
- 商談後の営業プロセスの効率や質
これらをチェックし、LPに本当に課題があるかどうかを見極めることが重要です。そうすることで、リソースの無駄遣いを防ぎ、効果的な改善につながります。
LP改善に使えるLPOツール
LPO(ランディングページ最適化)を効率よく、かつ正確に行うには、ツールの活用が不可欠です。
ユーザーの行動分析や、ページの表示速度チェック、ABテストの実施など、人力では見えづらい課題や仮説を裏付けてくれるデータを得られるのがツールの強みです。
ここでは、LP改善に役立つ代表的な3種類のツールを紹介します。

ヒートマップツール
ヒートマップは、ユーザーがLP上でどのように動いたかを「視覚的に見える化」できるツールです。特に、どこまで読まれたか(スクロール)・どこがクリックされたか(行動)・どこに注目が集まっているか(視線)など、実際のユーザー行動を数値ではなく“色と形”で直感的に把握できるのが特徴です。
| 主な機能 | 説明 |
|---|---|
| スクロール分析 | ユーザーがページのどこまで閲覧したかを表示。ファーストビューでの離脱が多い場合の改善判断に活用。 |
| クリック分析 | ボタンやリンクなど、どの要素がタップ・クリックされたかを可視化。CTAの有効性検証に役立ちます。 |
| マウスの動き分析 | カーソルの動きから注目されているコンテンツや視線の流れを推測可能。 |
【改善に活かせるポイント】
- ファーストビューでの離脱が多い場合は、キャッチやデザインの再検討。
- CTAボタンがクリックされていない場合は、位置・文言・デザインの見直しが有効。
- スクロールされていないエリアがあれば、コンテンツの削減や順序変更を検討。
【代表的なツール】
User Insight(ユーザーインサイト):日本語対応・UIが直感的で使いやすい
Mouseflow(マウスフロー):セッション録画機能も強力
Hotjar(ホットジャー):欧米で人気。視覚的に洗練されたUI
Clarity(クラリティ):Microsoft製。無料で多機能
導入コストも低く、最初に導入すべきLPOツールといえます。

LPの表示速度チェックツール
LPの表示速度は、ユーザーの離脱やSEOに直結する重要な指標です。特にスマホ環境では、読み込みの速さが成果を大きく左右します。
速度チェックツールは、LPの読み込みを遅くしている要因を特定し、改善案を提示してくれます。
| 機能名 | 説明 |
| ページ速度スコアの表示(モバイル/PC) | 閲覧環境ごとの読み込み速度を数値で可視化。特にモバイル表示の最適化に有効です。 |
| 重い画像やスクリプトの特定 | 非圧縮画像や過剰なアニメーションなど、読み込み遅延の原因を一覧で把握できます。 |
| 具体的な改善提案の表示 | 画像形式の変更、キャッシュ活用、リソースの圧縮や非同期読み込みなど、改善方法をわかりやすく提示してくれます。 |
【改善に活かせるポイント】
診断ツールの結果をもとに、以下のような施策を行うことで、LPの表示速度を大幅に改善できます。
- 画像の最適化
PNGやJPEGをWebP形式に変換し、ファイルサイズを圧縮。読み込み負荷を軽減します。 - コードの軽量化と非同期読み込み
不要なJavaScript/CSSの削除や、必要なタイミングでの読み込みにより初期表示を高速化。 - サーバー・CDN設定の見直し
CDNの導入や最適なサーバー配置で、通信速度の向上を図れます。
【代表的なツール】
表示速度のチェックには、用途やスキルに応じて以下のようなツールが使えます。
- Google PageSpeed Insights(無料)
モバイル/PC別の速度スコアを表示。改善点も色分けでわかりやすく提示。 - GTmetrix
海外環境での表示速度も計測可能。複数の評価軸で総合的に分析できます。 - Lighthouse(Chrome DevTools内蔵)
開発者向け。速度に加えてSEO・アクセシビリティなどもチェック可能。
まずはPageSpeed Insightsで現状をチェック → 指摘を元に改善、という流れが王道です。
ABテスト用ツール
複数のLPパターンを用意し、どのバージョンが最も成果を出すかを比較検証するのがABテストです。
LPOの施策効果を定量的に評価するには欠かせない手法です。
| 主な機能 | 説明 |
| 複数パターンの出し分けと比較 | 複数のLPパターンを同時に表示し、どのバージョンが最も成果を出すかを比較検証できます。 |
| CV(コンバージョン)目標の自動測定 | コンバージョン目標を設定し、達成状況を自動で計測・分析します。 |
| ユーザー行動の違いを可視化 | どのパターンでユーザーの行動が変わったかを視覚的に把握できます。 |
| 成果が高いパターンの自動最適表示 | 成果の良いパターンを自動で優先表示し、効果を最大化します。 |
【活用場面】
- キャッチコピーやCTAボタンのテスト
- 構成やセクション順の比較検証
- デザインや文言の微差がCVRに与える影響を確認したいとき
【代表的なツール】
- Optimizely:高機能・大規模サイト向け
- VWO(Visual Website Optimizer):ヒートマップなども併用可
- KARTE Blocks:ノーコード対応。ABテスト+出し分けも簡単
- ※Google Optimizeは2023年にサービス終了
ABテストを使えば、成果が出るまでの改善ループを「数字で回せる」ようになります。
ただし、一度に複数要素を変えると因果関係がわからなくなるため、「1回1要素」が原則です。

業界別のランディングページ改善成功事例
BtoBサービスでの改善事例
株式会社ウィルゲートでは、ランディングページの構成とデザインを見直すことで、コンバージョン率を大幅に改善することに成功しました。
旧ページでは成果が伸び悩んでいたものの、ユーザー視点に立ったファーストビューの設計や、情報を視覚的に伝えるインフォグラフィック調のデザインを導入。さらに、ABテストを通じて最適なパターンを選定した結果、CVRは269%改善しました。
BtoB領域でも、ユーザーの行動心理に基づいた情報設計が、成果につながることを示す好例です。
引用元URL:https://www.fwh.co.jp/works/339kz3831bb7/
EC・通販サイトの改善例
株式会社利他フーズが運営する「熊本馬刺しドットコム」では、ランディングページの構成と表示速度の最適化により、ユーザーの離脱率を改善し、CVR向上を実現しました。
従来のECサイトとLPを分離し、LPを別サーバーで運用することでページ表示速度を改善。さらに、キャッチコピーの見直しや、フリーページ機能を活用した構成改善により、直帰率を下げ、購買率を高めました。
顧客対応から得た「生の声」をLPや商品開発に反映させることで、ユーザー視点の情報設計を実現し、マーケティングとクリエイティブの連動が成果に直結した好例です。
引用元URL:https://www.future-shop.jp/magazine/interview-kumamoto-basashi
これらの事例は、業界やサービス形態に応じて、ランディングページを最適化することで成果が大きく向上することを示しています。改善施策を実行する際は、業界ごとの特性やターゲット層に合わせたアプローチが重要であることが分かります。
まとめ
LPO(ランディングページ最適化)による改善は、理論に基づいた戦略と実践的なアプローチの両方を組み合わせて進めることが必要です。ユーザー視点を常に意識しながら、アクセス解析やヒートマップなどを駆使して定量的な分析を行い、細かい改善を重ねていくことで、ランディングページのコンバージョン率(CVR)の向上や直帰率の低下など、継続的な成果を上げることが可能となります。自社のLPが抱えている問題点を客観的に評価し、優先順位をつけて効率的に改善に取り組むことが成功へのカギとなります。
ランディングページの改善にお悩みの方は、ぜひ弊社にご相談ください。貴社の課題に合わせて、最適なLPO戦略をご提案させていただきます。
「ランディングページ改善の極意|成果につながるLPO施策と成功事例を解説」
の詳細が気になる方は、
お気軽にお問い合わせください

Y's Blog 編集部