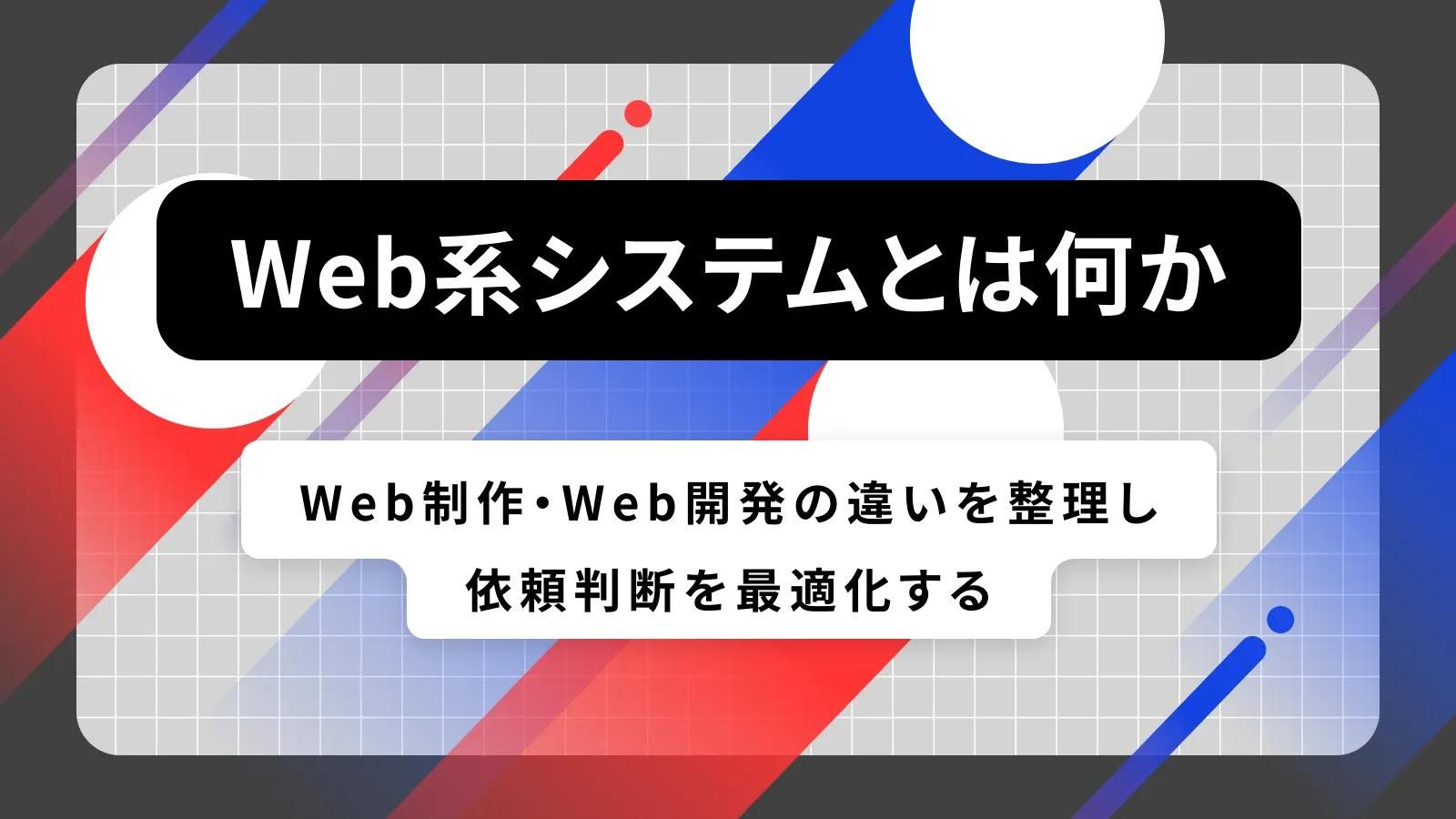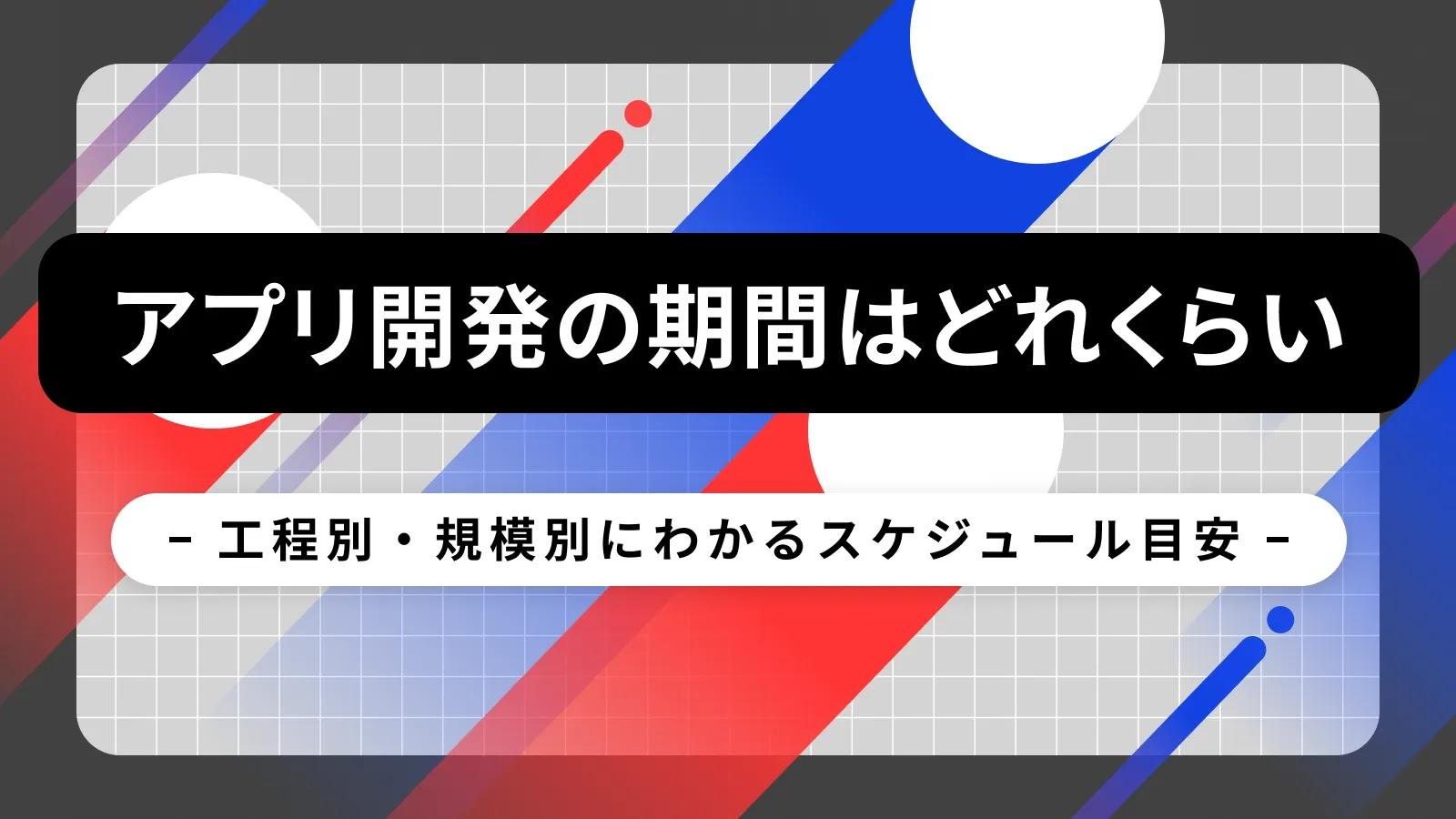Web運用保守とは?業務範囲・体制・ベンダー選びまで徹底解説
- Web制作

はじめに
「Web運用保守」とは、Webサイトの安定稼働と利便性の向上を目的として行われる一連の活動を指します。これには、日々のコンテンツ更新やユーザー対応といった運用業務に加え、サーバー管理、セキュリティ対策、トラブル発生時の復旧といった保守業務も含まれます。Webの技術やトレンドは日々変化しており、それに対応する柔軟な体制が必要なことから、Web運用保守の重要性は年々高まっています。
目次
Web運用保守とは何か
Web運用と保守の違い
Web運用と保守は似たような意味で語られることが多いものの、厳密には異なる役割と目的を持っています。
Web運用:Webサイトを利用者にとって常に価値ある情報源に保つための活動です。具体的には、
- ページの新規作成
- 既存コンテンツの修正
- 季節やキャンペーンに応じたビジュアルの変更
- フォームやバナーの設置・更新
- UI/UXの改善提案
などが含まれます。
Web保守:システムの安定性とセキュリティを確保するための活動です。以下のような業務が該当します。
- サーバーやCMSのバージョンアップ
- セキュリティパッチの適用
- データのバックアップと復旧
- ログ監視
- 脆弱性診断
両者は密接に連携しており、どちらか一方だけではWebサイトの品質を保つことはできません。運用と保守を統合的に管理することで、はじめて安定したWebサービスの提供が実現されます。
なぜ運用保守が重要なのか
Web運用保守の重要性は、単なる業務遂行の観点を超えて、企業全体のビジネス戦略と直結しています。Webサイトは、24時間365日稼働する「営業マン」ともいえる存在です。適切な運用保守が行われていない場合、次のようなリスクが発生します。
- ページ表示速度の低下 → ユーザーの離脱率の上昇
- CMSやプラグインの脆弱性放置 → サイト改ざんや情報漏洩などセキュリティ事故
- 検索順位の低下 → 自然流入数の減少 → 見込み顧客の損失
- 古い情報の放置 → ユーザーとの信頼関係低下 → ブランドイメージの毀損
これらは、企業の信頼性や収益に直接的なダメージを与える可能性があるため、継続的な運用保守体制の構築が欠かせません。
また、Googleなどの検索エンジンは、ユーザー体験やセキュリティへの対応も評価対象としています。つまり、適切な保守対応はSEO強化につながり、結果として集客数やCV率の改善に貢献します。運用保守は、Webサイトを長期的に成功させるための「土台」といえるでしょう。
Web運用保守の主な業務範囲
日常的な更新作業
日常の更新作業は、Webサイトの鮮度を保ち、ユーザーに最新情報を提供するうえで非常に重要です。具体的には、以下のような業務が含まれます。
- 新着情報やブログ記事の投稿
- 商品情報や料金表の更新
- シーズンごとのキャンペーンページの制作・公開
- 画像やバナーの差し替え
- フォームやCTA(コールトゥアクション)の最適化
特にCMS(WordPress、Movable Typeなど)を導入している場合は、コンテンツ管理や更新作業が効率化されているものの、操作ミスによる不具合や表示崩れなども発生しやすいため、十分な知識と確認体制が求められます。
また、SEOやCVR(コンバージョン率)向上を意識したテキスト修正や内部リンクの最適化なども、日常更新の一環として実施されるべきです。
トラブル対応と監視体制
Webサイトが突然表示されなくなったり、システムエラーが発生した場合、迅速な対応がビジネスへの影響を最小限に抑えるカギとなります。トラブル対応とそのための監視体制は、保守業務において最も重要な要素のひとつです。
以下のような監視・対応業務が日常的に求められます。
- サーバーの稼働監視(CPU負荷、ディスク容量など)
- 死活監視(Webページの応答確認)
- エラーログの自動通知
- アクセス過多やDDoS攻撃への対策
- システムの定期バックアップとリストアテスト
近年では、ZabbixやNagiosといった監視ツールや、AWS CloudWatchなどのクラウドサービスを活用することで、効率的な体制構築も可能となっています。障害が起きた際に即時に対応できる体制を整備しておくことが、企業の信頼性を支える重要なファクターとなります。
セキュリティ対策とアップデート
サイバー攻撃や情報漏洩のリスクが高まる中で、セキュリティ対策はWeb保守における最優先事項です。
主な対策項目には以下が挙げられます。
- CMS本体およびプラグインのアップデート
- セキュリティパッチの即時適用
- 不正アクセス検知ツールの導入
- SSL証明書の適切な更新と設定確認
- WAF(Web Application Firewall)の活用
- 管理画面のアクセス制限(IP制限や2段階認証)
特に、WordPressなど広く使われているCMSは攻撃の対象になりやすく、セキュリティの定期診断やペネトレーションテストの実施も重要です。社内に十分な技術者がいない場合は、外部ベンダーとの連携による対応が現実的です。
社内で行う場合の体制と注意点
必要なスキルと役割分担
社内でWeb運用保守を行う場合、以下のようなスキルと人材が必要になります。
- Webディレクター:全体進行とコンテンツ企画
- フロントエンドエンジニア:HTML/CSS/JSの修正・最適化
- システム管理者:サーバー・CMSの保守
- セキュリティ担当者:リスク管理と対策実行
- コンテンツ担当者:原稿作成と校正
すべてを一人でこなすのは現実的ではないため、業務の優先順位を明確にしたうえで、担当者間での役割分担と連携体制の整備が不可欠です。また、専門性の高い領域においては外部リソースの活用も視野に入れるべきでしょう。
どこまでを内製で、どこからを外注すべきか?
Web運用保守の業務には多岐にわたるタスクが含まれるため、内製と外注の境界線を引くことが重要です。判断の基準となる主な軸は以下の3つです。
| 判断軸 | 内製を検討すべき条件 | 外注を検討すべき条件 |
|---|---|---|
| 対応頻度 | 頻度が高く、社内での対応フローが確立しているもの (例:CMSの記事更新、定期レポートの作成) |
頻度が低く、その都度調査・準備が必要になるもの (例:年1回のSSL更新、障害復旧など) |
| 専門性 | 特別な技術を要さず、社内リソースで対応可能な業務 (例:画像の差し替え、軽微なテキスト修正) |
高度な技術や経験が求められ、社内で対応が難しい業務 (例:サーバー移行、脆弱性診断) |
| 緊急性 | 即時対応が必要でも、社内で迅速な対応体制を構築できる業務 (例:リンク切れ修正、軽微なUI調整) |
短時間での対応が求められるが、社内に即応体制がない場合 (例:サイトダウン時の復旧) |
ドキュメント整備と属人化の防止
Web運用保守では、属人化(特定の担当者しか対応できない状況)が深刻なリスクとなります。担当者が急に退職・異動した場合、業務が停止するおそれがあるため、作業内容を「見える化」することが重要です。
対策としては以下のような施策が効果的です。
- 業務フローのマニュアル化
- CMSの操作手順書の整備
- 更新履歴や障害対応ログの記録
- チーム内でのナレッジ共有会の実施
- 定期的なロールプレイによる担当交代訓練
こうしたドキュメントの整備は、社内の業務効率化と品質安定にも寄与します。
外部委託する際のポイント
業者選定の基準
外部にWeb運用保守を委託する場合、価格だけで業者を選ぶのは避けるべきです。選定にあたっては、以下の観点から総合的に評価する必要があります。
- 過去の運用実績や業界知見
- 提供サービスの幅(運用・保守・デザイン・開発)
- セキュリティ意識と対応体制
- 障害発生時のレスポンス時間
- 担当者とのコミュニケーションのしやすさ
信頼できるパートナーを選定することで、長期的な安定運用が可能となります。初期の段階ではトライアル契約や小規模案件から始めるのも有効です。
契約内容と費用の目安
委託契約においては、「どこまでが対応範囲か」を明文化することが非常に重要です。曖昧な契約内容はトラブルの原因になりかねません。
契約形態としては、以下のような形式が一般的です。
- 月額契約:一定の範囲で定常的な運用・保守を依頼
- スポット契約:必要なタイミングで個別に依頼
- チケット制:対応件数や時間に応じたポイント制
費用は業務内容・規模により異なりますが、中小企業のWebサイトでは月額3万円〜10万円程度が目安です。ECサイトや大規模メディアの場合は、それ以上の予算が必要になります。
Web運用保守でよくある課題と対策
よくあるトラブル事例
Web運用保守における典型的なトラブルには以下のようなものがあります。
- CMSアップデート後のレイアウト崩れ
- プラグインの競合による表示不具合
- ドメイン・SSL証明書の更新忘れによるサイト停止
- バックアップ不備によるデータ消失
- アクセス集中時のサーバーダウン
Web運用保守は、技術の進化が速く、新しいツールや手法が次々と登場する分野です。**「予防措置を講じておく」**という観点が重要ですが、それと同時に今後の変化に柔軟に対応できる体制の構築も不可欠です。特に、生成AIやSaaSの更新自動化など、新しい技術をいち早く取り入れることが競争力を高める鍵となります。
属人化・対応漏れの防止策
属人化の問題は多くの企業で共通して見られます。特に、運用担当者が多忙な場合や、兼任で業務を行っている場合に対応漏れが発生しやすくなります。
そのための対策としては以下が有効です。
- タスク管理ツール(Backlog, Trello, Asanaなど)の導入
- 定例ミーティングでの進捗確認と情報共有
- WBS(Work Breakdown Structure)による作業可視化
- 引き継ぎシートの作成と定期更新
これにより、業務の透明性と継続性を確保することができ、長期的な安定運用につながります。
まとめ
Web運用保守は、単なる作業の集合体ではなく、企業の信頼性とブランド力を支える重要な基盤業務です。トラブル対応やセキュリティ対策はもちろん、日常的な情報更新や体制構築によって、Webサイトはその価値を維持・向上させることができます。
自社だけでの対応が難しい場合は、信頼できる外部パートナーとの連携を検討しましょう。Web運用保守の仕組みづくりは、一度整えたら終わりではなく、常にアップデートし続ける姿勢が求められます。
弊社では、実績豊富な専門チームが貴社のWeb運用保守をトータルにサポートいたします。ご相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
「Web運用保守とは?業務範囲・体制・ベンダー選びまで徹底解説」
の詳細が気になる方は、
お気軽にお問い合わせください

Y's Blog 編集部